前回より。『機動警察パトレイバー the Movie 1/2』4K UHD BD/BDリマスター版公開&発売記念企画です。WWFさんの同人誌「WWF No.66 押井学会20『パトレイバー2』の話をしよう」に私(教官)が寄稿した「プラトンは正しかった」の続きです。繰り返しになりますが、内容はあくまで2023年当時調べた状況に従っています(ちょこっとだけ現在に合わせて修正しました)。
プラトンは正しかった 第2回
1993年前後の自衛隊
『機動警察パトレイバー2 the Movie』映画劇中で描かれている自衛隊と、現実の自衛隊を比較するという話に戻りましょう。当時と現在とで、詳しくない人でもすぐに気づくであろう変わっている点がひとつあります。
それは1993年に公開された『パトレイバー2』映画公開当時は「防衛省」ではなく「防衛庁」だった点です。
自衛隊設立の経緯から書き始めると長すぎますし本題とも逸れるので省きますが、最初は総理府、内閣府の「外局」として「防衛庁」がありました。それが国際平和協力活動、海上警備行動など任務の多様化などに伴い、2007年に「防衛庁」から「防衛省」に格上げされ、組織のトップは「防衛庁長官」から「防衛大臣」になりました。『パトレイバー2』設定上は2002年の話になっているから正しいのですが、仮にこれを現代でやるとしたら、劇中の航空自衛隊中部方面隊
また、幻の空爆を行ったとされる「F-16J」という機体ですが、この名前の航空機は存在しません。正確には「“F-2”に名前が変わった」と言うべきでしょう。当時、三菱F-1支援戦闘機の後継機として開発されていた「次期支援戦闘機(FS-X)」ですが、この機体はF-16をベースにした日米共同開発による新型機となりました。映画公開の1993年時点ではこのFS-Xが制式化された場合の名称が決まっておらず「F-15の日本ライセンス生産型がF-15Jになっているのだし、FSXもF-16Jになるのでは」という説が主流だったため、『パトレイバー2』でのF-16Jという名称がその名残となっているのです。ちなみに「支援戦闘機」とは一般的な軍事用語で言うところの「攻撃機(Fighter)」のことで、地上攻撃や対艦攻撃を行うための軍用機を指すのですが、「専守防衛」を旨とする自衛隊のため「攻撃」という言葉が避けられて「(地上戦や海戦を)支援(する)戦闘機」ということで支援戦闘機と呼ばれるようになったものです。一方でF-15など空対空戦闘を主体とする戦闘機は「要撃戦闘機」と言われました。なお現在は戦闘機のマルチロール(多用途)化に伴い、自衛隊の公式表記上ではF-2もF-15も「戦闘機」に統一されています。またF-2はF-15より機体が一回り小さく拡張性に乏しいなどの理由により、F-15よりも早く退役する予定となっています。
ちなみに、荒川が持ち込んだビデオに映っていた、実際にベイブリッジを爆撃したと米軍のF-16改「ナイト・ファルコン」は「最新型のステルス翼」「ごく最近開発されたベクタードノズル」を搭載しているとされます。一応推力偏向エンジン(ジェット気流の出力方向を曲げることによって高機動性を実現したもの)が組み込まれたF-16は実験機としては存在していますが、実戦配備はされていません。同時に「幻の空爆」のとき邀撃に上がった、カナード翼(小さい補助翼)とベクタードノズル(ジェットノズルを稼働させることで、ジェット気流の向きを変える)を搭載し、運動性能およびステルス性の向上がはかられたとされる空自のF-15改「イーグル・プラス」も実在しません。一応、コンフォーマル・ウェポンベイ(ミサイルなどを機体内部の兵器倉に搭載することでレーダー反射断面積を減らす)などのステルス技術を導入する予定だったF-15SEサイレント・イーグルがこれに近いでしょうか(カナード翼はないけど。メカデザイナーは本当にカナードが好き)。F-15Eストライク・イーグル戦闘攻撃機は非常に実績と評価が高い機体ですが、あまりステルス性が考慮されていません。この機体にある程度のステルス性を持たせる拡張を行ったF-15SEを、F-35よりも安価で提供できるとしてボーイング社が韓国など各国に売り込みましたが、結局F-35に敗れ去ってF-15SEの道は絶たれました。しかしイーグル・プラスはまだしもナイト・ファルコンまで『パトレイバー』グッズとしてプラモデルが出るとは思いませんでした、ナイト・ファルコンなんて劇中にはほんの僅かなシルエットしか出ていないのに……。
なお現実においては、自衛隊のF-15Jのうち改修が困難な初期型を除く機体は、近代化改修されてまだまだ使われる予定です(ただしカナードもベクタードノズルもつきません)。
amazon.co.jp F-15J改 イーグル・プラス
amazon.co.jp F-16J
amazon.co.jp F-16改 ナイト・ファルコン
もうひとつ、荒川が所属する「陸上自衛隊幕僚監部調査部第二課別室」は実在した組織で、「調別」の名で知られていました。ただこの組織は1997年の防衛庁(当時)情報本部設立に伴う組織改編により「情報本部電波部」となったため、『パトレイバー2』の作中設定である2002年時点では既に存在していません。さらに調別は陸幕の組織とは言いつつも、実際には主に警察庁の人間によって構成されている内閣情報調査室(内調)の下部組織に近く、調別の室長も警察官僚が務めているため、荒川が本当に調別の人間なら、最初から警察組織と無縁の人間ではないということになるはずです。もともと戦後日本の情報活動は公安の活動、つまり主には赤軍派などの取り締まりのためのものから出発しているため警察庁の影響力が強く、旧陸軍情報部にいた人間を中心に作られた組織が母体である調別にも、公安が影響力を及ぼしていたようです。ところが実際には内調も警察庁からは距離を置かれており、内調室長経験者も「警察でさえ、いい情報は絶対、内調には伝えない」と発言しており、警察庁にとって所詮内調は〝子会社〟扱いだったそうです(「軍事研究2006年9月号別冊ワールド・インテリジェンスVol 2 日本の対外情報機関」ジャパン・ミリタリー・レビュー)。
日本の官僚組織のグダグダは置いておいて(置きたくないですが……)、調別はどういう組織かということに話を戻しましょう。調別は
調別の通信傍受能力は高く、1983年にアメリカのアラスカ・アンカレッジ空港を出発した後、韓国・ソウルに向かっていたはずがソ連領空に迷い込んだ、乗員・乗客269人が搭乗していた大韓航空ボーイング747型007便(もちろん民間機)がソ連軍に撃墜された「大韓航空機撃墜事件」にて、ソ連軍の通信を傍受していました。この通信には007便撃墜前後の、「目標を撃墜した」といったパイロットと地上のやりとりが含まれていました(当初調別はソ連軍機が何を撃墜したのか判らず、演習だと思っていました)。007便の行方不明が明らかになっても当初ソ連は事件への関与を否定しておりましたが、日本から傍受記録を渡されたアメリカは証拠として国連安全保障理事会にてこの記録を公表。結果ソ連は、007便の撃墜を認めざるを得なくなりました。その後もすったもんだがあるのですがその事はまた後に少し触れるとして、ともかくこの事件で調別は有名になりました。
ここまで書いたとおり調別はSIGINTを行う組織であり、それが国内の不穏な「あるグループの内偵」を行っていたというのは、元々特車二課を利用しようとしていた荒川による創作だったとしてもかなり変な話です。本来であれば「不穏なグループの内偵」みたいな仕事は警察庁、公安の仕事になってくるはずなのですが、その点は調別の有名さや「自衛隊の情報関係の人間」という立場のわかりやすさ、ストーリー展開などを考えて無視されたのでしょう。『パトレイバー2』制作当時はそのあたりの情報、調別の実体がわかっていなかったためかもしれません。
なお現在の防衛省情報本部でも、人から届いた情報を分析する「分析部」はありますが、HUMINTで直接情報を集める部署は存在せず、HUMINTは国内から国外の活動を含めて内閣情報調査室、法務省公安調査庁や警察庁警備局などの担当であるということになっています。もっとも日本の情報活動におけるHUMINTは情報収集も防諜も、戦前はかなりの規模で活動していた一方で戦後になってはお寒い限りと何度も言われています。
ただアメリカなどと軍事情報を共有するのに「日本はちゃんと防諜活動を行っている」とアピールするため、外交や防衛、対テロ活動などにとって重要な「特定機密」を漏洩する、あるいは資格のないものが収賄、脅迫行為、不正アクセスなどによってこれを取得しようとすることを禁じる「特定秘密の保護に関する法律」通称「特定秘密保護法」が2013年にようやっと制定されました。これで機密情報を持つ人間に対し「機密情報を売ってくれ、たっぷりカネを払う」「情報を渡さないとお前はひどい目に遭うぞ」とそそのかしたり脅したりするスパイ自体を禁じる法律がやっと戦後日本にもできたわけです(それまでは、情報を持つ人間が漏洩することを禁止し、場合によってその人間に罰則があるだけでした)。ですが他国では民主国家であろうと、国家や国民に重大な危機を与えかねないスパイ活動、情報漏洩については死刑や終身刑もあり得るのが一般的なのに対し、特定機密保護法違反の罰則は「10年以下の懲役」と非常にぬるいもので(それでもマスコミや左派はギャアギャア騒ぎ立てましたが)、防諜、特にスパイ活動に関する捜査活動もどこまで行われているか非常に怪しいものです。
ただ一部のソ連の外交官などは冷戦時に徹底的に尾行、マークされて諜報活動ができないため、やむなく帰国したという話を私は読んだことがあります。そもそも外交官は現在の法律でも不逮捕特権で守られますが、外交官であるがゆえ身元をはっきりさせざるを得ないので直接行動はできませんから、実際の諜報活動は「手足」となる人間を操って行います(それゆえに“スパイマスター”という言葉があるのです)。さて日本でその「手足」となっている外国のスパイはどれだけ捜査されているのでしょう? 戦前では、有名なゾルゲ事件のように、実際にスパイを逮捕したこともあったのですけど。
『パトレイバー2』解説文章についてはまた気が向いたら続きを掲載します。あったら次章「変わりゆく自衛隊
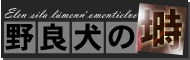
コメント