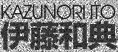|
■プロフィール ■作品書庫 ■伊藤和典雑記帳 ■エージェントの独り言 ■寺子屋 ■掲示板 【広間】 ■掲示板 【座敷】 ■リンク ■トップページへ戻る |
■TECH Win 連載原稿 『戸浦芭瑠伝説』
| 序 |
|
初めて飛騨を訪れたのは、もう10年近く前のことになる。そのときは、いかにも観光地
めいた町の印象に、たぶん二度とこの地を訪れることはないだろうと思ったものだ。とこ
ろが、後に結婚した相手が飛騨高山の出身だった。必然的に、何度か脚を運ぶことにな
り、いつのまにか自分も、定住者に近い眼で飛騨を見るようになっていた。
岐阜県北部――東に北アルプス、西に白山連峰、飛騨路も、みな山の中である。にもか
かわらず、旧石器時代、ここにはすでに集落が存在した。飛騨が中央勢力のもとに服属し
たのは5世紀以降になってからのことだと推測されている。中世には“飛騨匠”の伝説を
生み、近世、江戸初期には京都の文化が、中・後期になって江戸の文化が移入されると、
今なお“飛騨の小京都”と呼ばれる高山を中心に、独特の旦那衆文化が形成される。
春、秋の高山祭に使用される“屋台”は、こうした背景があって生まれた。祇園祭の山
鉾にも似た壮麗な山車は、内部に精巧なからくり人形を持つものもあり、見るものに、こ
の造形を生みだした文化の厚みを感じさせるに充分なものだ。
祭りの時でなくても、屋台会館に行けば、その実物を見ることができる。
――今にして思えば、そもそもの発端は、この屋台会館の展示品の中にあったのだ。屋
台を飾る彫刻の、下絵として描かれた“竜”。それが、飛騨への興味をかきたて、あれを
見つけさせることになったのだから。
一般に、日本で“竜”といえば、長崎おくんちの蛇踊りに見られるような、長いヘビ型 のものをさす。電光またたき雷鳴とどろく黒雲の中、身をくねらせて空を駆ける水神―― それが日本の竜のイメージだ。 下絵の竜も、確かにそのイメージを踏襲している。踏襲はしているのだが、なんと、そ の背には“翼”がはえていた。西洋のドラゴンが持つ、蝙蝠のそれのような薄い飛膜でで きた翼。 一口に竜といっても、蛟、蜃など、竜にはいくつかの種類がある。ここで、その詳細に ふれることはしないが、東洋の竜と西洋のドラゴンが合体したような、こんな竜はかつて 見たことがない。いったい、なぜ、ここにこんな竜が存在するのか? さらに、そのつもりで屋台を見ると、そこに装飾された竜のほとんどが、いわゆる竜と は別のものであることに気づく。圧倒的に多いのは“応竜”と呼ばれる、きわめてマイ ナーな竜なのだ。『三才図会』(鳥獣五巻)に、「恭丘山に応竜がいる。応竜とは翼のあ る竜である」とあるように、この竜も翼を持つ。が、その姿は、羽毛のかわりに鱗をはや した鳥の身体に、竜の頭部をくっつけたようなデザインで、竜というよりは鳥のイメージ が強い。 どうひいき目に見ても、いわゆる竜の方が、デザイン的にも、ずっと優れていると思 う。にもかかわらず、屋台を飾るのが応竜なのはなぜか? 思えば、飛騨は不思議にみちている。 高山の南西にある位山は、飛騨を日本海斜面と太平洋斜面に分かって東西に連なる分水 嶺のほぼ中央に位置し、山頂付近には謎の巨石群が散在する。 丹生川村の両面宿儺の伝説。白川村には、地震による地滑りのため、莫大な黄金ととも に一夜にして埋没したという帰雲城の伝説。 さらには、幻の飛騨王朝伝説――飛騨高天原説まで存在する。さすがに、ここまでくる と、どうかとも思うが、シュリーマンのトロイ遺跡発掘の例を出すまでもなく、伝説はつ ねになにがしかの真実を含んでいる。この天と地との間には、人の知識などの想いもよら ぬことがある。 義父を相手に、屋台会館の竜の絵に始まって、こうした飛騨の事など、とりとめのない 話をしていたときのことだ。 「一度、蔵の中を見てみますか」 茶のぬくもりをいとおしむように渋草焼の湯飲みを両手で包んで、義父がいった。飛騨 の4月は、まだ寒い。 彼女の実家は、高山の北郊、市内からは車で20分ほどの距離にあった。そのつもりにさ えなれば、おそらくは、かなり過去まで系図をたどれるであろう旧家で、庭先から江戸時 代のものと思われる分銅がでてきたりする。家そのものも飛騨特有の合掌造りでこそない が、へたなワンルームマンションよりも広い土間や、黒光りする太い梁、高い天井が、い かにも時代を感じさせる。そんな古くからの家だから、蔵の中に、何か興味をひくものが あるかもしれない――妻の出産に立ちあうために、実家までついてはきたものの、退屈し ているらしい私への、義父の気配りだった。 母屋から離れて建てられたその蔵は、切妻の屋根で、妻側に家紋をあしらった日本に典 型的な土蔵だ。土壁を厚く塗った耐火構造のため、江戸時代中期以降、街の商家を中心に 発達、普及し、しだいに農村でも造られるようになったものだという。 かすかに、湿った土の匂いのする蔵の中は、外気の変化の影響が少なく、思ったよりも 暖かい。1階には、季節のものや、普段は使わない家族のものが、きちんと整理されてし まわれている。義父の性格なのだろう、昭和30年代の古い雑誌や、子供たちが学生時代に 使っていた参考書などまで、しっかりと残してあるのに驚かされる。収納がなにかと話題 にされる都市の住宅事情からは考えれられないことだ。 階段がなく、2階は梯子を使って昇り降りする。そこには、裸電球の灯りに照らされ て、大小さまざまな木箱が並んでいた。そのほとんどは、お膳や皿、小鉢など、大勢の来 客があったときでもなければ、めったに使われることのない食器類だという。 「古いだけのガラクタみたいなもんですが、思い立って整理してみようかとすると、 ほぉ、こんなもんもあったんか――というようなものが出てくることもあります」 「勝手に見せてもらって、いいですか?」 「どうぞどうぞ。なんかあったら遠慮なく、声かけてください」 義父が梯子を降りていくと、あらためて多数の木箱をながめ、さて、どこから手をつけ ようか……と、無意識のうちに煙草をくわえていた。 「火の元だけは充分、注意してください」 梯子の途中で引き返したらしい義父が、昇降口から顔だけ出して、こっちを見ていた。 もともと、探すものがはっきりしていたわけではない。別に、何かが見つかると思って いたわけでもない。それは、ただの暇つぶしのはずだった。 そう、油紙に包まれた2枚の写真を見つけるまでは―― 正確には、それを写真といっていいものかどうかさえ判らない。銀板写真の実物を見た ことはないが、どうやらそれに近いものらしいとは察しがつく。それは、鈍い光沢をもつ 金属板に焼き付けられていた。 1枚は、どこかの民族衣装らしきものを身につけた二人の男女。男の方は30代半ばくら いの日本人だが、女性の方は若く、国籍不明。表面の埃をはらえば、鮮やかなカラーで、 ほとんど退色していないことも不可解なら、金属板の裏に刻まれた文字も、また不可解 だ。 『文蔵、流里、万延六年 婆羅迦にて』 後で調べたことだが、万延六年という年号は存在しない。万延元年(1860)の翌年、干 支は辛酉だった。古代中国に、辛酉の年は革命が起こるという説があり、日本では901年 を延喜と改元して以来、わずかな例外をのぞいて、辛酉の年には歴代改元することになっ ていた。そのため万延元年の翌年(1861)にも改元がおこなわれ、元号は文久にかわる。 万延六年という年は、さらに2度の改元を経た慶応元年(1865)にあたる。 もう1枚の写真は、さらに怪しい。鳥のようなものが写っているが、これはいったいな んなんだ!? 文蔵という人物、婆羅迦(バラカ?)という地名について義父に訊いてみたが、心当た りはなく、2枚の写真も初めて見るものだという。が、自分の家の蔵に、そんなわけのわ からないものがあるのも気持ちが悪いから、と、翌日、わざわざ寺まで出向いて過去帳を 調べてきてくれた。 帰った義父はひどく無口だった。 たかだか百数十年前――予想できたことではあったが、文蔵氏は、我が義父の曾祖父 だったのだ。私の場合、父方の曾祖父、曾祖母ともに、生まれたときにはすでに他界して いたが、母方は両方とも健在だった。曾祖母に遊んでもらった記憶すらある。三代前と は、それほど近い存在なのだ。写真の人物が、義父の曾祖父なのかどうかはともかく、義 父は、それまで自分の曾祖父について何も知らなかったこと――何も知らされていなかっ たことがショックだったのだと思う。 『文蔵 天保三年出生 万延元年 神隠し』 寺の過去帳には、そう記載されていた。 それから、義父と私との蔵あさりが始まった。文蔵氏のことを、もっと知りたかった。どんな些細な手掛かりでもいいから、ほしいと思った。蔵の中は、あらかた探しつくした ものの、それ以上のものは、ついに見つからず、二人とも、これまでとあきらめかけたこ ろに子供が生まれた。義父にとっては初孫だ。 「無事に生まれたことを御先祖に報告――」 途中まで言いかけた義父が、あ!という顔をした。仏間――先祖のものなら、そこに あってもおかしくない。 こうして、それは奥の間に一段高くしつらえられた、間口一間の大きな仏壇の中から発 見されることになる。 写真と同じように、油紙に包まれた1冊の写本。表紙の文字は『戸浦芭瑠覚書』と読め る。「日清戦争より帰還せし兵士の持ち来りしものなるが、その内容、俄に信じがたし。されど親の記したるものとなれば、徒やおろそかにもできず、後世に残すものなり」義父 の祖父にあたる人物の手によるメモの添えられた、この本の詳細については、次回にゆず る。が、それにしても、これは…… どのような経緯でか、文蔵氏は海難事故にあい、ある島に漂着したらしい。『戸浦芭瑠 覚書』は、その島の見聞録のようなものだが、その内容は、メモにもあるように、およそ 信じがたいものだ。 外界とは、まったく異なった生物相をもち、ウルモ・ルンリンと呼ばれる聖域を中心に 機能するこの島には、大洪水以前の知識と技術が存続し、島に残る伝統は唯一無二の原初 の伝統であり、世界のすべての伝統の根本となったものだ、と文蔵氏は記している。氏に よれば、およそ2000年前、東方よりベツレヘムを訪れた3人の博士も“戸浦芭瑠”からの 使者だったというのだ。これは、壮大な悪ふざけなのか、それとも……。 つづく |