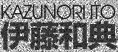|
■プロフィール ■作品書庫 ■伊藤和典雑記帳 ■エージェントの独り言 ■寺子屋 ■掲示板 【広間】 ■掲示板 【座敷】 ■リンク ■トップページへ戻る |
■サンサーラナーガ ムック原稿 『輪廻の竜』
| 序章 |
|
雨はいつもと同じ時間に降ってきた。 居住区を取りまく水路と南北に配された沐浴場。小高い丘をなす総社の門前にある蓮 池。そして、竜のための水場――龍苑は四方を険しい山岳に囲まれながらも水が豊富だ。 夜の闇に冷え切った大気が、朝の光に暖められると、そこかしこの水面から靄が立ち昇 り、そびえる岩肌を濡らす。やがて、湿った大気は雲を呼び、驟雨となって水面に帰る。 龍苑――それは街の名であると同時に、その中央に位置する巨大な石の伽藍を擁する建 築物の一群をさす名でもある――が始まって六千年、それはこの山間の小都市で毎日繰り 返されてきた光景だった。 「怒られるかな……」 苔むした山門の下で雨を避けていた小さな子供がつぶやいた。いつもなら雨が降りだす 前に家に帰っている。今日は、帰宅が遅れてしまったことを言っているらしい。 この数カ月、目が覚めると山門を訪れるのは、彼の日課のようになっていた。 この子供、まだ赤子のころに自分の身体ほどもありそうな卵にしがみついて山門の前で 泣いているのを拾われたという。 卵は竜の卵だった。 口さがない人々は、あるいは若い竜使いが、やむにやまれぬ事情から生まれたばかりの 子供を捨てたのではないかと噂しあった。 卵が彼の出自を知る、唯一の手がかりだったのだから、これは無理もない噂と言えた。 竜使いの威信にかけて、ギルドが調査に乗り出したが、真相はついに究明されることが なかった。 ごく一部の例外を除き、ほとんどの竜使いはギルドによって管理される。未登録の竜使 いは盗賊も同然のクズレ竜使いとみなされた。クズレてしまえば、宿泊、エモノの換金は もとより、町の人々と話をすることすらままならなくなる。 ギルドが与える竜使いの称号は、竜というきわめて危険な生きものを連れ歩くための免 許証といえた。免許をもたないクズレ竜使いやモグリの竜使いは、危険な存在として、社 会の一員とは認められず、逆に、ギルドの竜使いは人々に畏怖と敬意をもって迎え入れら れた。 ギルドは、竜と人とが安全に共存するために、なくてはならない存在だったのである。 そして、龍苑はこのギルドの総本山でもあった。ここにのみ『龍』の文字が使用される のは、そういうわけだ。 竜と竜使いによって成立する龍苑である。竜の卵を抱えていた以上、素性が知れぬとは いえ、捨て置くわけにもいかず、赤子は子供のいない老夫婦の元にあずけられた。そのと き、大人たちは子供を卵から引き離そうとしたが、赤子は母親の乳にしゃぶりつくよう に、けして卵から離れなかったという。 通常、竜の卵は百日で孵る。が、赤子の抱く卵は百日が過ぎ、二百日が過ぎても一向に 孵るようすがなかった。 ――これは死卵であろう。 老夫婦は、卵を処分しようとしたが、このときも子供はひどく泣いて抵抗し、卵を取り あげることはできなかった。 彼は、つねに卵とともにあった。 眠っているときでさえも、身体のどこかが卵に触れていないと、子供はすぐに泣き出す ありさまだった。すっかり子供に情が移った老夫婦は、卵に万一のことがあれば、子供も 無事にはすまないのではないか――と、いつしか、卵を失うことを恐れるようにさえなっ ていた。 そんなころ、子供は卵をささえにしてつかまり立ちをするようになる。不安定な卵は当 然のごとくころがり、彼も転倒する。あまりに何度も同じことを繰り返すので、老夫婦は 卵を四角い升に乗せることで、子供の転倒と卵が壊れることを予防した。 が、子供が歩けるようになると、危険はさらに増大する。ただ歩くさえもおぼつかない 子供が、卵を持ち歩こうとするからだ。 老夫婦は大きな袋にボロ布とともに卵をいれ、子供の肩にその袋をかけさせることで問 題を解決しようとした。はじめ、卵はまるで重石のように子供の動きを束縛したが、彼は 一向に気にする様子がなかった。 竜の卵の入った大きな頭陀袋を下げた小さな子供は人目をひいた。 ――あれが、あのとき山門に捨てられていた子供か…… その姿は、人々の忘れかけていた記憶を呼び覚ました。記憶は時間の経過によって修飾 をほどこされ、子供は若いクズレ竜使いに捨てられたことになっていた。 ――あいつは、クズレの子だ…… 同年代の子供を持つ親たちは、自分の子供を彼に近づけたがらなかった。また、彼に甘 い老夫婦は、彼をあまり外に出したがらなかった。それで、とりわけ不都合もなかった が、子供も、いつもでも家の中にばかりいるわけにもいかない。 遠慮のない子供たちの言葉によって、彼が捨子だったことを知ったとき、小さな変化が 起こった。 ――自分は何者なのか? 自分はどこから来たのか? 自分はなぜここにいるのか? 捕らえどころのない、もやもやとした彼の疑問を整理すれば、こういうことだったろ う。日課のように、竜の卵とともに自分の捨てられていた山門を訪れるようになったのは それからのことである。 山門のひさしから落ちる雨滴が作る水たまりを足でかき混ぜながら、子供は切れた頭陀 袋の肩紐をおもちゃにしていた。雨が降りだす前に、家に帰れなかったのはこの紐のため だ。切れた紐を結べばいい――子供には、そうするだけの知恵も技術もまだなかった。唐 突に紐が切れ、突然、腕にかかる卵の重さが増したことに当惑し、ぐずぐずしているうち に雨が降りだした。 雲が瘠せれば雨はやむ。そうなるまで、さほど時間はかからないはずだった。が、その わずかの時間が、子供にはひどく長く感じられる。かといって、雨の中を走っていこうと いう発想も彼にはない。 退屈しはじめた子供は、山門の内側に眼を向けた。ギルド総本山としての龍苑がにぎわ いをみせるのは、雨が上がった後である。今はただ雨にけむる石造りの伽藍と、池を取り 囲む緑に包まれた美しい庭園だけが、ひっそりとそこにあった。 池のほとりに紅い葉を繁らせる、ひときわ大きな竜樹の傍らに人影が見えた。少女とい うにはまだ幼く、女の子というにはどこか大人びたその人影には見覚えがあった。 子供はずり落ちそうな卵を抱え直して、彼女の方に足を向けた。 「……生まれたときから自分の卵を持っているおまえが、うらやましい」 気配に振り向いたアムリタが、彼を認めてそういった。口元は微笑んでいたが、澄んだ 切れ長の眼はどこか寂しげで、子供はどう答えていいかわからず、曖昧な笑みを浮かべた だけだった。 「私は、また、卵がもらえなかった……」 彼より三つほど年上の彼女は、独り言のようにつぶやいて池に眼をもどした。 この彼女、早くに両親を亡くし、龍苑付属の竜使い養成所に、手伝いをしながら寝泊ま りしているという。亡くなった彼女の両親は名のある竜使いだったが、その死には多く謎 が残されていた。 子供は老夫妻の次に、彼女が好きだった。この土地で彼に親しく話しかけてくれるのは 老夫妻を除けば、彼女――アムリタしかいなかった。 子細は判らないまでも、彼女が落胆しているようすだけは彼にも理解できた。なんとか 力づけてあげたいと思いつつも、子供の貧弱な語彙では適当な言葉がみつかるわけもな く、彼は、おずおずと彼女の袖を握りしめた。 アムリタが彼を見おろすと、かすかな衣擦れの音ともに、ほのかな竜涎香の薫りが漂っ た。今度は、彼女の顔に優しい笑みが浮かんでいた。子供は、ただそれだけで嬉しく、白 い歯を見せて破顔した。 「その卵、早く孵るといいな…… 竜には、さまざまな言い伝えがある。その卵にして も、誰も調べようとさえしないが、あるいは、けしておろそかにはできないものなのかも しれない……」 「重いの…… 卵」 「育ってるんだ」 「竜の赤ちゃん、生まれる?」 「いつか、きっと」 こんなことをはっきりと言うのはアムリタだけだ。アムリタが、そういうのなら、きっ とこの卵からも、いつかは竜が生まれるのだろう。子供はそう信じることにした。もしか したら、自分が卵を必要としているのではなく、卵が彼を必要としているのではない か…… ふとそんな考えさえよぎったが、もちろんそれは明確な形を取るには至らなかっ た。 「人は竜を求め、竜、これに従いて、ともに滅ぶべし―― この言い伝えが意味するもの はなにか?」 山肌を這うように流れる雲を見つめて、アムリタは言葉をついだ。 「それ以前に、竜はどこから来て、どこへ行くのか? そもそも、竜使いとは――竜と は、いったいなんなのか? 私はそれが知りたい。私はそれを知るために竜使いになる」 子供には難しすぎる話だが、それでも彼は自分が興奮しているのが判った。熱を出して 寝込んだとき、身体がとめどなく膨れ上がり、どこかへ浮遊していってしまいそうな感覚 にとらわれたことがある。今の彼も、それと似た感覚を味わっていた。 竜はどこからきたのか? 自分はどこから来たのか? 竜使いとは、竜とは何か? 自 分は何者なのか? それが知りたい――大好きな彼女は、自分と同じようなことをやろう としているのか? 「おまえのその卵が孵ったら、その竜と私の竜と、おまえと私と、一緒に謎を解いてみな いか?」 子供を見つめるアムリタの表情は真剣だった。 ――これは、とても大事なことなのだ。 彼はアムリタをまっすぐに見つめて、力強くうなずいた。 「約束」 「ああ、約束だ」 池で鯉が跳ね、水面に波紋を広げる。小さな揺らぎに池を覆う蓮が細かく震え、葉の上 に踊る雨の雫がひとつの大きな水滴になって池に帰った。 いつしか雨が上がり、雲の切れ間から差し込む朝の光が、龍苑を囲む山々をオレンジ色 に染め上げる。 山の向こうには別の世界がある。子供は、いつか老夫婦から聞いた話を思い出してい た。世界を貫く巨大な柱“シュメール”の礎をなすのが、ここ龍苑。その上にはムシュフ シュ。さらに上にブール。そしてプリー、ナーガ霊園…… 子供とアムリタは、まだ見ぬ 世界と彼らの旅に想いをはせた。 子供は帰宅が遅れたことなどすっかり忘れていた。 アムリタ、この時わずかに八歳。 二人が旅立つまでには、さらに十年の歳月を必要とする。 アムリタが彼女の竜を得たのは、一二歳の年である。世界に異変が起こりだしたのは、 そのころからだった。龍苑の雨が不規則になり、健康に生まれてくる竜がめっきり減っ た。町の外には以前にもまして怪物が跋扈し、上の世界との往来が不自由になった。人々 は“シュメール”が軋みだしたのだと囁きあい、今にもっと悪いことが起こると眉をひそ めた。 そんな中で、若くして天才と謳われたアムリタに、いつしか龍苑の期待が寄せられるよ うになる。 そして―― アムリタがたった一人の叛乱を起こした運命の日。彼女の放った火が龍苑の空を赤々と 染めたその夜、けして孵ることがないと思われた竜の卵に亀裂が走った。彼の竜が生まれ たのだ。 |