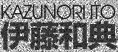|
■プロフィール ■作品書庫 ■伊藤和典雑記帳 ■エージェントの独り言 ■寺子屋 ■掲示板 【広間】 ■掲示板 【座敷】 ■リンク ■トップページへ戻る |
■ドラゴンマガジン連載 『武蔵野妖精迎撃隊』
| 第1話 |
|
フリーアルバイター・藤堂麻子(一八才)は貧乏だった。
にもかかわらず、乙女座、B型、弱点不明、性格・雨の日の仔猫、身長一五九センチ、
体重内緒、B八六、W五七、H八七の体内のどこにも、「あぁ、わたしは貧乏だわ」とい
う認識は存在しなかった。早い話が、彼女は自分が貧乏であることを知らなかった。
産まれるとき、すでに両親ともいなかったといわれるが、どういうことなのかよくわか
らない。また、もうひとつの話では、彼女は四才で産まれた、ということになっている
が、こちらのほうは、もっとわけがわからない。
が、とにかく彼女には、街やリゾート地を徘徊、もしくは浮遊する同年代の女たちとは
明らかに異質のなにかがあった。
一六の春に東京に出てきて、西荻窪に四畳半の部屋を借りた。川端で湿気と西陽がきつ
く、アパート全体が目に見えるほど傾いていて、部屋の引き戸はかってに開くし、共同ト
イレの内錠は人が入っていなくてもかってに閉まるという老朽アパートだったが、家賃が
安いことと、これを人に貸そうという発想に感動して、麻子はほとんどためらわなかっ
た。
しかし、都心の地価上昇にともなって、商売に不熱心な大家も、さすがに考えたら
しい。
「あのぉ、申しわけないけど、ここねぇ、取り壊してマンション建てようと思う
んだ。でね、半年間家賃タダにするから、その間にほか捜して引越してもらえないか
なぁ」 大家が、ひどくすまなそうにいいにきたのがちょうど六ヶ月前だった。 「ま、いいか」 モルタルの剥げかけたボロアパートを見上げて、麻子がつぶやいた。スタイリストの助 手みたいなことをやったときにもらった、バカでかいバッグの中に着替えが少々。彼女の 荷物はそれしかない。 所持金壱萬五千とんで六拾四円。貯金ゼロ。いまだ新居はみつからず、いざとなったら このでっかいバッグを寝袋がわりにすりゃぁいいや、と安直に考えて、麻子はアパートに 背を向けた。 クリスマス間近か、風がいっそう冷たさをます黄昏どきだった。 ちょうどそのころ…… 大森高志(三五才)は怒っていた。 麻子がいたアパートから五〇メートルと離れていない所に止まったワゴン車の中であ る。 <佐藤クリーニング>、ボディにはそう描いてあったが、注意深く見れば、それがクリー ニング店の車でないことは、すぐにわかった。 クリーニング店の車が8ナンバーのわけ がないし、その運転手がアライアのスーツを着たブロンドの女性なわけもない。 ウィンドにスモークガラスを使ったその車の後部で、白衣をはおって、唇の端に微笑み のカスをぶらさげているような顔をした男が 大森にヨロイを装着していた。中世の騎士たちが愛用し、いまやロールプレィングゲーム には欠かせないアイテムとなった、あれである。 「待て、こら、ちょっとまてっ!」 「なんでおまっかいな?」 語気を荒くした大森に、白衣の男が怪しげな関西弁で応じた。 「おまっかいな、じゃないっ!なんなんだこれはっ、おれはコスプレに行くつもりも、 アバタールになるつもりもないっ。こんな格好で町ン中を歩けるか!ガキが笑う。ジジバ バが憐れみの目でおれを見る。いやだ。おれはいやだ!」 「しかしなぁ……」 二人のやりとりを聞いていた、大英帝国の残り香を身にまとったような老人が、立派な アゴ髭をしごき、ついでに髪の毛までしごいていった。 「その姿、しゃれていてよいと思うのだが、不服か?」 「おれが喜ぶとでも思ったのか」 「きっぱり、思った」 「せやけど、あんた、これがないと、たちまちはかなくなりまっせ。おっ死ぬことうけ あいやで」 「う〜む……お、そうだ!名案がある」 「聞きたくない」 たじろぐ大森を無視して、老人は得々と語った。 「この季節、サンタクロースなら目立たぬぞ。さっそくこれを−−」 「準備はまだなの?」 いらだちを含んだ声で、運転席の女がいった。まるで声優のように達者な日本語だっ た。 「改造は無理や。時間があらへん」 「誰もおれのことを考えてくれない」 「あたりまえだ」 「とにかく、はやくしなさいっ」 運転席の女が血走った青い目を向けたとき、それまで後ろの座席に正座して瞑想にふ けっていた髪の長い女が、静かに口を開いた。 「帰りましょう。気配が消えました」 大森はホッと胸をなで下ろし、ブロンド女はとても活字にできないようなスラングを吐 き捨てて、ダッシュボードの上の車の香水を叩き壊した。 藤堂麻子とこの奇妙な五人組。 彼らは○○行ほど先で出逢うことになる。 麻子は清潔な白い大理石の浴槽で思いきり手足を伸ばした。浴槽はそうするのに充分な 大きさがある。ブラインドの隙間から、新宿副都心の超高層ビルの明りが見えた。 一一階建てマンションのペントハウス。 マンションのオーナーが金にものをいわせて作った、三LDKの屋上家屋に麻子はい た。 あの日、アパートを後にした麻子は駅に行く途中でペットショップにたちよった。小動 物が好きで、この店にはよく顔をだしていた。麻子にしてみれば、顔見知りの動物たちに 挨拶をしていくつもりだったのだろう。 「さよなら」と。 ところが、病気の仔猫を見つけたために、運命が変わった。 雑種の仔猫が数匹、小さな檻の中でかたまって震えていた。そのうちの一匹が目ヤニと 鼻水で顔を汚している。明らかに風邪だった。猫の、とりわけ仔猫の風邪は命にかかわ る。麻子は店の親父にそのことを話し、すぐに病気の仔を隔離して、治療するように頼ん だ。 しかし、主人の反応は冷たかった。 猫が雑種だったこともさることながら、麻子が、いつもひやかしに来るだけで、何ひと つ買ったことのない客だったことが、主人の態度をいっそう硬化させたのかもしれない。 麻子はねばり強かった。怒鳴りたくなるのを懸命にこらえて、なんとか説得しようとガ ンばった。が、 「そんなにいうんなら、お客さんが買ってって治してあげればいいじゃない」 親父の無慈悲なひと言には、唇をかんで黙るしかなかった。 『暴れてやろうか。大暴れして、その隙に檻の中のチビを助け出すチャンスは、どのく らいあるだろう……』 などと物騒なことを考えているときに、幸か不幸か、仲裁が入った。 ドッグフードを注文にきていた、藤色のヘアピースが嫌味にならずによく似合う、上品 なお婆さんが、正義は麻子にあり、と裁定を下したのだ。 相当なお得意さまらしく、親父はすっかり恐れ入ってお婆さんに頭をさげ、仔猫は麻子 の望みどおりに扱われた。 そのうえ、麻子はお婆さんに気に入られ、夕飯に招待される、というオマケがついた。 家の門構えを見ただけで、お婆さんがただのお得意さまでないことは、すぐに解った。 どうやら、このあたりの大地主らしい。で、ご飯を食べながら、世間話をしているうち に、麻子はペントハウスに住むことが決ってしまったわけだ。 「孫のために作ったんだけど、アメリカに行っちゃってねぇ。ほったらかしとくのもな んだから、あんた、管理人がわりに住んでおくれよ」 さすがに、麻子も遠慮したが、家を出たときには、しっかりキーを持たされていた。 「まぁ、いいか」 とりあえず、つぶやいて、お婆さんが描いてくれた地図をたよりにマンションに向かっ た。 想像したより、はるかに豪勢なペントハウスだった。ドアを開けて、ロココ調のその居 間を見たときには、思わず、逃げ出そうかと思ったほどだった。 「うわぁ、こりゃだめだ……むいてないや」 肩からずり落ちたバッグを引っ張り上げ てドアを閉めようとしたとき、電話が鳴った。ベル六回分ためらって、ポリポリ頭をかきながら受話器をとると、 「もう、ついたころだと思ってねぇ。どうだい、きっと気に入ってもらえたと思うけ ど」 うれしそうなお婆さんの声が聞こえて、麻子は観念した。 「え、えぇ、でも、あたしにはもったいなくて。あの、部屋を汚したりすると……」 「いいんだよ。そりゃ生活すれば多少は汚れるだろうけど、家は人が住んでるほうが痛 まないからね。気にしないで使っとくれ」 と、電話は切れた。 それから五日ほどたつが、結局、麻子は居間にあるソファーの周辺とバスルームしか 使っていない。日中、お天気のよいときには屋上庭園でアルバイト情報誌をめくり、夜は ただひたすら部屋の広さをもてあまして呆然とする……そんな、おしりがむずがゆくなる ような日々を過ごしていた。 「ん?」 シャンプーした髪をすすいでいた麻子は、シャワーを止めて、耳をすました。 ドアチャイムが鳴ったような気がしたが、気のせいだったろうか。それとも…… しばらくじっとしていると、今度は、かすかだが確かに、ドアの開く音がした。 「お婆ちゃん、ようす見にきたのかな」 濡れた髪をゴシゴシ拭くと、麻子はバスタオルを身体にまきつけて浴室をでた。 「お婆ちゃん?」 そのまま居間にいくと、ヨロイを着た男があわててテーブルの下に隠れようとして、し たたか頭をぶっつけた。 「誰?」 「し、失礼。私は怪しい者ではない」 説得力のカケラもない。 うろたえる男にくらべて、麻子のほうが、はるかに落ち着いている。 「泥棒さんじゃなさそうだし……」 「違う。もちろん、違う。が、そういうあなたも"あめちゃぶの尻"ではなさそうだ」 「あめちゃぶ? なに、それ?」 「いや、なんでもない、なんでもない」 「怪しい」 「そんなことはない。それは気のせいだ。きみはきっと、疲れているんだ。疲労は正常 な判断力を惑わす。私は、たとえて言うなら、通りすがりの正義の味方みたいなものなん だ。論理のみを用いて客観的に判断しようとするなら、あれほど怪しいものもない。が、 健全な肉体に宿る健全なる精神と直感力をもってすれば、それが善であることは、たちど ころに了解できるはずだ。どうやら私は姿を現す場所をまちがえたらしい。まちがいは、 速やかに修正されなければならない。では、そういうことで、さらば」 男はぐちゃぐちゃとしゃべくりながら、玄関までもどりドアを開けた。一歩、外に踏み 出そうとしたところで、ふと、立ち止まり、麻子に背を向けたままで、言葉をつづける。 「よけいな世話かもしれないけど、一人暮らしなら、戸締りはちゃんとしておくべき だ」 「しといたもン」 「した?」 ヨロイの男がゆっくりと麻子のほうを見た。 「うん」 麻子が邪気のない顔でコックリした。 「開いてたぞ」 「またかぁ……」 「また?」 麻子の口から、答のかわりにクシャミがとびだした。 「あ、すまん」 男はドアを閉めて麻子に向き直った。それから、いいにくそうに、 「ものは相談だが、おれはココアを作るのが得意だ……」 私が、おれ、にかわっている。 「髪を乾かした後で、ココアを飲みながら詳しく聞かせてくれないか」 ヨロイを着た男がミルクパンと泡立て器を手にしてキッチンに立ち、真剣な表情でココ アを作る姿というのは、どうひかえめに見ても、やっぱり異常である。 セーターを着た麻子は床にあぐらをかいてこみあげる笑いをこらえながら、頭を乾かし ていた。 「すると、ドアチェーンをかけても、朝にははずれてるわけか」 「そう、かけたばっかりのドアチェーンが目の前で、ピョンってはねたのも見たよ」 「ほかに変わったことは?」 「う〜ん、そうだなぁ……」 麻子はドライヤーのスイッチを切って頭を振ると、天井を見上げて考えた。 「ねぇ……電気って、つまる?」 「つまる、とは?」 「鼻がつまるとか、下水がつまるとか、いうじゃない。日本語知らないの?」 ココアのカップを持って、男が居間に移ってきた。 「ふつう、電気はつまったりしないぞ」 「そっか……」 ポツリといってココアをすする。 「んまい!」 「アーモンドがあれば完璧なんだがな」 「へぇ〜、すごいんだね」 「電気の話」 「うん。あのね、夜中にドアチャイムが鳴るの。出てみると誰もいないんだ。そんなこ とが何回もあって、あたし、お昼にいないことがあるから、そんとき誰か来て押したチャ イムの音がつまってて、夜になると出てくるのかなぁ、と思ってたんだ」 「なんてこった……」 男がひとり言のようにつぶやく。 「まちがいじゃなかった。あいつらの言うとおり、ここにいやがるんだ」 「え?」 「電話、貸してくれ」 男は立って、受話器に手を伸ばした。 と、突然、テーブルに置いたカップが割れて、ココアが飛び散った。 どの窓も閉まっているのに、部屋の中に風が吹き、麻子の髪を逆立てた。 電球がたよりなくまたたいて、ふいに闇が訪れ、どこか、意外に近いところで、ひどく 不安をかきたてる、地の底から一気に天空まで突き抜けるような、叫びとも呻きともつか ない声がした。正確には声かどうか定かでない。むしろ音というべきだろうか。 男が悲鳴を上げたのが、それとほとんど同時だった。 そして、静寂。 「だいじょうぶ?」 麻子が声をかけると、男は咳き込んでなにやら悪態をついた。 麻子は手さぐりで窓辺に行き、カーテンを開けた。月の明りが部屋に差込み、頭のてっ ぺんから爪先まで、濡れてぬらぬらと光る男を照らしだした。 あたりには、むせかえるほどに、錆臭い血の匂いがたちこめていた。 「一九八七年は、実に不可解な年でした」 エスメラルダ・パークスと名のるブロンドの女性は、まっすぐに麻子の目を見つめて、 ゆっくりと語りだした。見事に鍛えあげられた筋肉質の身体に、うっとおしほどの自信と 生気がみなぎっている。ヨロイを脱いだ男、大森高志と並ぶと、野性の女豹と路地裏の捨 て犬、あるいは毛の抜けたライオンぐらいの差があった。 麻子は大森を救出(?)に来たエスメラルダにつれられて、いまだ武蔵野の面影を残す 住宅街にある、この家にやってきた。 表札がわりに出された"超地球研究所"という小さなプレート以外には、これといって 特に変わったところのない、ごく普通のコロニアル風一戸建て建売り住宅である。 その二階にある二〇畳ほどの居間で、麻子はエスメラルダの話を聞いていた。 「日本では史上空前の水不足とともに記録的な猛暑がつづいたかと思えば、それが一 転、涼しく冷たい夏に様変わり。梅雨があけないうちに立秋をむかえる地方さえでてくる ありさまでした。中国奥地では体長一五メートルにおよぶ巨大な魚が発見されたばかりで なく、二メートル一六〇キロの獣人を射殺した、という事件も起きています。中国だけで なく、遠く海を隔てたカナダでも、ビッグ・フットの目撃例があいつぎ、世界中の空には UFOが飛び交い、月は神々の前進基地だと主張する者もでてきました」 何度も繰り返し話したセールストークのように、まったくよどみがない。エスメラルダ は、麻子に話の内容を咀嚼する時間を与えるつもりでか、そこで言葉を途切らせた。 が、麻子は、彼女の話よりも、国籍不明の民俗衣装らしきものを身にまとい、部屋の隅 で結跏趺座して、うつろな目を宙にむけ、時折、うなずいたり、首をかしげたりしている 髪の長い女性、神宮寺蛍に興味を持ったようだった。 エスメラルダは小さな咳払いをひとつして、大きな声で先をつづけた。言葉使いが急 に、ぞんざいになっている。 「気づいてる者は、まだまだ少ないけど、これらの出来事は、現在、世界的規模で進行 しつつある大異変の、まぁ、前ぶれみたいなものなわけ。この動きが本格化すれば、私た ち人類に未来はないわ。わかる?」 わからない。麻子には話が大きすぎた。 「あは、あははは、な、なんだろぉなぁ」 麻子は助けを求めるように、横で剃り残した顎の髭をいじくっている大森に目をむけ た。 「妖精だってさ」 ちょっと気恥ずかしそうに、大森がいった。 「ようせい?ゴラスとか?」 「そういうのは知らんが、ケルト、ラテン系の民間信仰でフェアリー。ゲルマン系では エルフと呼ばれてる連中だ。一八世紀末、産業革命とともに人々の前から姿を消した妖精 たちが、今になって、また動きだしたらしい」 「へぇ……いいな、それ」 「わしもそう思うのだが、その姉さんの考えは違うんだな」 大英帝国の残り香男、自他ともに認める最後の博物学者、末光純一郎がはいってくるな り、そういった。 「あたりまえよ。彼らの存在を認めたら、私たちの科学体系は音をたてて崩れていく。宗教と哲学の一部だって、無事ではすまないわ。これだけでも大変なのに、錬金術をたし なむ妖精がでてくれば、経済が死ぬ。夜空で妖精が恋を語らえばスクランブル発進が増え る!新たな戦争が起こる!あとには破滅の二字だけよ」 興奮したエスメラルダがバンッ、とテーブルを叩くと、どこかで赤ん坊が泣きだした。蛍がいそいそと立って、開いていた窓を閉めにいく。なにしろ、ここはありふれた住宅地 なのだから…… 「最悪の事態を回避するには」 落ち着きをとりもどして、エスメラルダがつづけた。 「彼らの活動が本格化する前に、妖精たちを見つけしだい、抹殺、殱滅するしかな い……誰かが、やらなければいけないのよ。世界の平和のために。あなたたちも、もっと 選ばれた戦士としての自覚を持ってちょうだい」 「え?え〜っ、ここ、そういうとこだったんですかぁ?」 「因果よな。たかが妖精ごときの出現で崩壊する程度の社会なら、いっそのこと、いち からやりなおしたほうがいいと思うのだが」 「口をつつしみなさい。何を考えようと勝手だけど、仕事はきちんとやってもらいま す。ところで、末光」 「はかせ」 「末光博士。分析はすんだの?」 「いま、河田がくる」 いっているうちに、濡れた手を手拭でふきながら、白衣の男、通称アルカイック・河田 が入ってきた。この男、寝ているときも、怒ったときも、いつも笑っているように見える ので、こう呼ばれているが、本名を知るものはひとりもいない。 「あれな、あの血。馬の血や」 「馬の血。すると、やはりバケツで運んだものであろうな」 いわくいいがたい沈黙のあとで、大森が口を開いた。 「それは、まじめな話か、それとも、ただのダジャレか?」 「ひぃみぃつぅぅぅ」 末光は、にぃ〜、と笑って髭と髪をしごいた。恐るべきくせ毛というべきか、二房に分 かれて横にひろがった顎髭と、二房に分かれて逆立った頭髪が、X字型になっている。 余談だが、大森は末光が"ドクター・X"というペンネームで深夜放送に投稿している のを目撃したことがある。どうやら、学界にうけいれられない自説をラジオの深夜番組で 発表しているようだった。 「やっぱり、あめちょびの尻、とかいう妖精のしわざなの?」 「あめちょび、ではない。あめちゃぶ、だ」 とても大人の会話とは思えない。だが、 麻子は真剣に聞いていた。 「あのぉ、なんなんですか、それ」 「あめちゃぶの尻といってな。名前と、それがとてつもなく恐ろしいものだという伝承 のみが残っていて、実体は皆目わからん。聖書以前の妖精だ。つい、このあいだも、そい つを追い詰めたのだが、逃げられてな」 「それが、あそこに?」 「むはは、あめちゃぶの尻は馬の血で警告したりせんよ。うむ。声を聞いたといった な。ちょっと来なさい」 末光が先に立って案内したのは、地下室だった。家の中で、唯一、研究所らしい場所と いえた。一〇畳ほどのスペースに、何に使うのか定かでない機械が散乱し、かすかに醤油 の匂いがするのは、カップ麺の容器が片ずけられずに、ほったらかしにしてあるせいだろ う。 「そこ、足元気ぃつけてや」 河田にいわれて、麻子が足元を見ると、階段から降りたところの床が大きく陥没してい た。その中心に、なにかのおまじないか薬のカプセルが置いてある。と、思ったら、 「薬ちゃいまんねん。機械やらなんやら、そない小さぁくしたら運ぶの楽やろ思て、縮 めたんやけど、大きさ変わっても、質量変わらん。わやですねん。こら、反重力装置と セットにせなあかん、てなもんで試作したのが、これや」 これ、とは壁ひとつをまるごと占領している悪魔じみて巨大な機械のことのようだっ た。 「うまくいかんわぁ……あ、所長には内緒でっせ」 「なにが内緒ですって?」 エスメラルダも地下室に降りてきた。 「また、こんなに散らかして!週に一度は掃除しろと、あれほど−−」 「小言は後にしてもらおうか」 末光がエスメラルダを遮った。 「河田くん。君のおもちゃに楽器があったろう。あれを弾いてくれ。ソ#・シ・二オク ターブ上がってソ#・フェルマータだ」 言われたとおりに、河田はシンセサイザーを弾いた。 「あ、これ……!」 麻子と大森が顔を見合わせた。 「やはり、これか。ヴァイオリンの音色でヴィブラートをかければ、もっと似るぞ」 河田がシンセサイザーを調整して、もう一度弾くと、そのとおりになった。 「これはな、バンシーの声だ。泣き女、悲しみの洗い手、ともいう。まれに、死をもた らす者となるが、多くの場合は、人の死を悼んですすり泣く無害な、むしろ哀れな妖精 だ」 「で、どうすればいいの?」 「なにもせんほうがええ」 「ノォ。ビジネス」 「おまえ、ろくな死に方せんぞ」 末光はグリッと首を九〇度傾けて、エスメラルダを見上げた。なにしろX頭の人だから こうしてもシルエットがほとんど変わらず、えらく気色悪い。末光博士のX攻撃である。 「やめいっ!」 「ふん……バンシーの撃退法などというものはな、ないのだよ。だが、まぁ、ひとつだ け……」 「あるのね」 エスメラルダが末光につめよった。スーツの下の筋肉が盛り上がっている。 「バンシーは……」 「バンシーは、なに?」 「成人前の娘のパンティーに弱い」 河田がシンセサイザーに頭をぶつけて、不協和音が鳴り響いた。 「末光……」 「は、か、せ」 「やかましい。それが真面目くさって言うことかっ」 「だまらっしゃいっ!」 飛び散る唾がエスメラルダを制した。 「よろしいか。我々が相手にしているのは、腕のひと振りで人間をカエルに変えたり、 シャレではないぞ、緑の石ころに変えたりする連中だ。そおゆう族に、まっとうな論理が 通用すると思うか?思うまい!」 一応、スジは通っている。 いつのまにか、みんなが麻子を見ていた。 「えぇと、あたし、そろそろ帰り−−」 後ずさる麻子の腕をエスメラルダがムズとつかんだ。 「協力してくれるわね」 「いやです」 「あのペントハウスは好意で借りてるっていったわよね。馬の血で汚れた絨緞はどうす るのかしら?」 「……まいったなぁ」 麻子は深い深い吐息をもらした。 その夜、"超地球研究所"のメンバー全員がペントハウスに集まった。 大森はヨロイのかわりにパンティーをつけた釣り竿を持っている。 「わいの発明が、こないな布切れ一枚にかなわんとは、あぁ情けない」 「あたしも情けないな。妖精退治とか、してほしくもないのに。どぉして−−」 「これを振り回すおれのほうが、よっぽど情けない。正気の沙汰とは思えんぞ」 「そりゃあ、しゃあない。あんたは、そおゆう役目の人なんやから」 「あのなあ……」 そのとき、 「来ます」 蛍がおごそかに宣言した。 地鳴りのような震動とともに電気が消え、サラウンドでバンシーが泣いていた。 交差する懐中電灯の光の中で、ヤケになった大森が、釣り竿を振り回す。 末光は下から自分の顔に明りをあてて、呪文とも、戦いの歌ともつかないものを唱えて いる。語感から察するに、ポリネシア系の言語であるらしい。 椅子が床をすべり、食器が中を舞い、空間から小石が降り注いだ。 その中を、蛍が、しずしずとバスルームに逃げていく。 バンシーの声がひときわ大きくなって、再び、大森の上に大量の血が落ちた。 エスメラルダがハリウッドふうの悲鳴をあげて、あたりに静けさがもどった。 「う〜む。大森、敗れたり」 エスメラルダが末光の後頭部をはたいた。さらに、文句のひとつもいおうかとしたとき、 「あ」 麻子が小さくつぶやいて、ドアの外にでた。そして、彼女は見た。屋上庭園の椿の根方 で、ひとりの女が背中を丸くしてうずくまっているのを。 それがバンシーだろう、と麻子は直感した。彼女には、バンシーがひどく苦しんでいる ようにみえた。かわいそうに思って、麻子は一歩一歩バンシーに近付いた。 色あせた金の薄物を身にまとい、両肩を覆うぼさぼさの長く紅い髪は、地面にまでとど いている。最初は老婆かと思ったが、柔らかそうな形のよい腕にのせた横顔は、まだ若 い。 どう声をかけようか、と麻子がためらっていると、ふいにバンシーが振り向いた。 真っ赤に泣きはらした目は、新月の沼地のように暗く、冷たく、その底には、虚無と絶 望とを秘めていた。 麻子はそっとバンシーの肩に手をおいた。 予想に反して、その肩は熱かった。 バンシーが麻子に手を伸ばした。 「だいじょうぶ……」 麻子がささやくと、バンシーの顔が、わずかにゆがんだ。バンシーは微笑もうとしたの かもしれない。 風がバンシーの長い髪と薄物をなびかせ、次の瞬間、バンシーは、まるでシャボン玉が はじけるみたいに、その姿を消した。 空でかすかに、あの声が聞こえたが、それもすぐに、淡く街の明りを反射するぶ厚い雲 にすいこまれて消えた。 「逃した?」 ペントハウスの戸口に立って、一部始終を見ていたエスメラルダがつぶやいた。 「いいえ、消えました」 いつのまにか、蛍も横にきている。 「消滅、ゆう意味でっか?」 「むはは、あの娘、ただ者でない」 「どうでもいいけど、おっさん……パンティーの話は、でまかせだろう?」 「ふふん」 末光は鼻で笑って、答えなかった。 「あ、雪だ」 バンシーの消えた夜、東京に例年より早い初雪が降った。 ちょっとばかり切ない気分になって、いつまでもいつまでも、雪の降る空を見上げてい た麻子が、翌日、風邪で寝込んだことはいうまでもない 。
つづく |
■参考:“ケルト妖精物語”W.B.イエイツ 編井村君江 編訳ちくま文庫 |